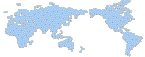
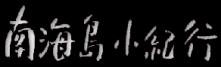 30回
30回
スールー海アリーナ環礁

|
|
町は活気に満ちていた。 人々は、荷を背負い、自転車をこぎ、ジプニーというフィリピン独特の小型乗合バスにぶらさがるまで、一杯に乗っている。 「外にぶら下がって乗っている人は、ただなんです。」と町の案内役をかってでてくれた在住ウン十年の久保さんが言う。僕等もこのジプニーを一台チャーターして乗っているわけで、窓が無くて、フロントガラスの部分が前に開くものだから、風が髪がゆれる程、入ってくる。 「あれ、ボディだけ買ってくるんですか?」 道端にブリキでできたブランクボディが転がっている。 「エンジン、ドライブ等は別ですけど、後は全部作っちゃうんです。自分達の都合のいいように作るんです。アメリカとスペインと東南アジアを足して、ミキサーの中に入れて ぐるぐるとやると、ジプニーになるんですね」 「一体、このパナイ島、イロイロ市の人口は、どのくらいなんですか?」 久保さんは、若いのか年寄りなのかはっきりしない、とにかく顔がかなり黒くて、ぼさぼさ頭の運チャンに聞いてくれた。そして何回も聞き返して、指で0の数をもう一度数えて答えてくれた。 「アバウト、600万人。何回も聞き返して、確かめたんですけど」とさすがの久保さんも驚いている。 まあ、マニラ市やセブ市は知られているが、ここに名古屋より大きな町?があったなんてアジアってすごいなァーと自分の知識の無さをカバーしたように感心してしまった。 |

|
このイロイロ港を午後4時に出航して、300km離れている目的地、アリーナ環礁に次の日の朝に着くのである。350トンのサザンクルーズ号は10ノットちょっとで、ゆっくり走りだし、 「始め、サザンクロス号って名前を付けたらしいです。それがね、キリスト教の国だから字数の13という数がだめで、あわてて、クロスをクルーズと一字増やしたそうです。」「でね、もともとは日本の弓削高専の練習船で、弓削丸です。」と久保さんは言う。 出航して2時間程で、素晴らしい夕陽がスールー海に沈んだ。デッキの上で 寝ていると久保さんが、 「あれが、南十字星ですよ」と指をさす。 「ああ、あの大きいやつですか?」と僕は上に一等星のように輝くのを見つけて言うと、「あれはにせ十字星です。本物は、その下の小さく、ボーッと光っているやつですよ。 八重山からも見えるんじゃないですか。」 「5〜7月頃、コンディションが良ければ、見えるみたいですけど。それも八重山の最南端の島、波照間島あたりが一番です。」 八重山では、南十字星を、はいむるぶしと言い、はいは南、むるは群れ、ふしは星を意味する。要するに南の星の群れということになる。 「こっちの言葉では、何というのですか」 「カサドパン,ちなみに北に見える北斗七星は ベトンペッセル」 海に生きる人々にとって、この2つの星々は、古代より、大きな道しるべであった。 北斗七星を目指し、北上し、南十字星で南下するといった、南島海洋文化は、きっと南十字星の見える北限である、八重山諸島にまで、伸びていったに違いないのである。 |

|
翌朝、カラカラという錨を降ろす音で目が覚めた。朝5時30分である。船室の窓の外はまだ暗く、ザァーザァーと小さな波がぶつかる、音が聞こえるだけだ。コーヒーを一杯飲んでから、リアーデッキに出てみると、ちょうど僕等の乗る25ftぐらいのボートを降ろしている。アリーナ環礁は、中央部に小さな灯台があって、そのまわりに水上住宅ともいえる、白いやぐらを組んだ家が連なっている。灯台は石で出来ているものの、上が平らになっている。たぶん焚き火か、アーク灯のような火炎式光源をおくのであろうことが、遠くから見ていてわかった。 朝もやは、序々に溶けていく。と、強烈なオレンジ色の朝日が上り始めると、ひんやりしていた外気も、一気にあせばむ湿気のように体にまとわりついてきた。 「波が高いけど、どうでしょうか」と小林さんがちょっと心配そうな顔で波に揉まれているテンダーボートを見ている。 「じゃあね、若いの3人連れて行くから、泳げる人、手を上げて。」と冗談のような本気のようなことを言うと、橋本君、山口君、そして本田君がおそるおそる手を上げた。 かくしてオペレーターは、ダニーという26歳の若者。そして僕と若い3人の釣り師が飛び出して行ったわけである。とりあえずは、リーフエッジ沿いに風上に向かい、行ける所まで行って、下って来ようという戦略をたてて、走りだしたわけであるが、15分もしないうちに、波がボートの前から少しずつ入って来た。 ダニーは、ちょっとスピードを緩めて、それを乗り切りだしたので、僕もほっとした。 40分位走ると、母船はかなり小さく見えるところまできた。ちょうどこの大きなリーフの流れだしが、風と同調して、波が立っていないところに来たので、ボートを寄せた。 安全のために、エンジンは止めず、エッジ沿いに風下に流す方法を取る。一投目から、キャスティングした全員のルアーが、海上から、消し飛んでしまった。 |


|
フッキング! なんだよこれ、かんべんしてよ! アアーはずれちゃった! あ、また来た。ともう若いやつらは大喜びであって、一番後ろでそれを見ていたダニーも、にやにやと笑いだした。何匹、GT.を釣ったのだろうか、すでに20kgオーバーも数本ランディングできている。風は朝より、凪だし、波はさらに低くなってきた。強烈に太陽がじりじりと容赦なく照りつけてくるものの、気温はあまり上がらないみたいだ。 「石があるだろう。ああいうメリハリのある所に、GT.のでかいのが付いていることがあるんだ。」ほら、前が急に深くなっているけど、右側に流れ出が有るだろう。」と 本田君に指を指して教えると、彼は、僕の指の方向にフルキャストを試みた。ルアーは石の向こうの浅瀬まで飛び、ゆっくりと引き出した。くねくねと海中を泳ぎ、パコンと、浮き上がって、空気をたくわえて、ダイブする。さらに大きめの泡が、軌道をトレースするように、航跡となり、プチプチと水面で破裂する。深みに入ったルアーは、ブルーの背が濃青色の海の中にくっきりと見えた。その瞬間、丸みを帯びた三角形の巨大な頭が、まるで原子力潜水艦のように水を左右に分けて、押し進んで来た。本田君は落ちついていた。ルアーを失速させて、魚を追いつかせ、更にかすかなショートパンピングをしたとたん、重々しいボコッという盛り上がりとともに、ルアーは一気に呑み込まれてしまった。 「何か、とてもでかいね」と言うと、 「全然、今までのと違うみたい。ライン止まりません。!」と言いながら、ドラッグ テンションを更にアップしている。僕はダニーに指示して、深みの方にボートをゆっくりと移動させた。 ラインは更にゆっくりと出ていくが、魚がこちらを向いたに違いなく、序々に沈みだした。アームポンピングでゆっくりと魚を寄せ、フットポンピングで魚を浮かせるが、またラインを出される。一進一退の攻防が10分程続いた。 |


|
ショックリーダーが見えてきたので、僕は、ぐいとつかんで浮かせにかかるが、なかなか浮かばない。まだ魚は元気である。やっと浮かせて、たっぷりと空気を吸わせて、尾びれのつけ根をグイとつかんだが、手が回らない程太い。仕方なく両腕をまわして持ち上げにかかったが、3分の2のところまで上げてから 「ケイ君(橋本君)、ちょっと手伝え、一人じゃーあがらない。」 やっとの思いで、2人がかりで魚をボートの上にあげた。 写真を撮ろうと、そのまま抱っこしようとしたが、大きすぎる。仕方なく、尾をもって、パチリ。ケイ君に頭を海の方に出してもらって、ドボンとリリースした。 「一体何kgぐらいあったですかね?」と虚脱感に襲われているが、嬉しさが顔をひきつらせている、本田君が僕に聞いた。 「長さはね、1m30cmぐらいだけど、すごい太さだよね。僕もね大概のでかいやつは1人で持ち上げるけど、今日はだめだったね。36〜37kgというところじゃないか」 昼食と軽い昼寝を済ませて、メンバーを少し入れ換えて午後の部が始まった。梅原さんが新しいメソッドのショートパンプ用ロングペンで、スローにポンピングを始めると、従来のペンシルが全部ティザーになったように、面白いようにヒットさせている。ペンシルは速さが命だから、同じ飛距離であれば、このルアーが残るわけで、カスミやアカマスといった小物が、ティザーみたいなペンシルを追いかけていってしまった後、スローポンピングをされるのだから、深場にいたGT.が浮上して、我慢できず思い切りヒットするわけである。 「梅ちゃん、普通のペンシルの3倍ヒットしているよ」と呆れ顔で、小林さんが言っても「これはね、力要らないし、疲れないし、いいよ」とルアーから目を離さない。そのうちまたドカン。 今度は僕のルアーがリーフエッジの浅場でヒットしてしまった。 「鈴木さんヤバイですよ」と本田君が心配してくれたが、僕は200LBを3.5m、 130lbを4m,PE20号を2mという、超ロングショックリーダーをとっているから、そのまま止めて、リーフに沿って走らせる。海中の障害物を大小、見ながら、じわじわとGT.の頭をアウトサイドに向ける。リーフエッジから出た魚を一定の距離、そのまま、表層で泳がせてから、深みにもってゆき、ぐいと引き寄せると、深く送りだした。 後はボートの真下まで、引き寄せて、パワーリフトを上げる。小林さんに素早くランディングしてもらい、リリース。。 「船も動かさないで、3分ぐらいで、何か呆気ないですね。」とまだ疲れの取れない本田君は不服そうである。 |


|
新月の夜は、真っ暗である。船のあかりに小魚が群れだすと、イカやトビウオが集まってきた。 それをクルーの一人が網ですくったりしている。 江森さんがルアーで小型のギンガメアジを釣ったので、つられて皆、小さなミノーやジグを投げ始めた。明かりの向こうのリーフエッジで、ドカンというバイトが、時折聞こえる。 「あそこまで、ルアーが届けばねェ・・・」と誰かがつぶやいている。 僕は夕食の時のビールが急に回ってきて眠くなってしまった。 「元気の良い諸君、お休みなさい。」と言ってクーラーの良く効いた船室に帰った。 |
