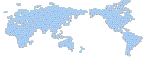
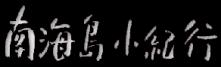 36回
36回
小笠原釣紀Ⅱ

|
|
小笠原を初めて見た人間は? ハワイ諸島あたりのポリネシア系の人かもしれないし、小笠原の南のはずれ、硫黄島から出土した古代石器は、サイパンやグァム島あたりの南方マレー系石器とよく似ている。 また、ボルネオやフィリピンから北斗七星を目指して北上した人々が、なんらかの理由で琉球列島からそれて小笠原諸島に至ったのかもしれない。いずれにしても、初めに発見したのは太平洋の海の民であろう。 その後、江戸時代に入って小笠原島探検の船が出されるようになった当時は、小笠原とは呼ばずに、ブニン(無人)とかブジン島と呼んでいた。 これがなまって、国際的にはこの島々をボニンアイランドという。 言うまでもなく、今回お願いした三徳丸船長、吉田謙吉さんも、その一人であったことは前回書いた通りである。 |
|
|
ランディング・リリースとは? 「これじゃ、かえしがないじゃないか!」と、一度怒られてしまったが、初めに説明をしなかった自分が悪いと思って、あやまって、改めてやらせてもらうことにした。 熱心に努力してくれる船長には、やはり、どんなことでも相談すべきだとつくづく思った。 「逃がしてやるなら、頭を海の底に向けて、いっきに潜っていけるようにすりゃ元気にもとに戻れるなぁ-」と細かいアドバイスをしてくれるこの人は、よほど魚が好きなんだなと、僕はふと思った。 それを、人間のまた釣りたいという欲望と、一方的な偏愛と自己満足とによって、逃がす、リリースしてやることになる。釣られて前より元気になった魚など、いやしない。 |

|
|
釣りは、何尾釣ったかではなく、どういう釣りをしたかである。 「10ozのジグで、でけぇ-イソマグロ!」と、僕もつられて、はしゃいで、ハイスピードのディープジギングを3人で頑張りだすと、すぐに次々とヒットする。 |

|
150㎏のヒラガシラ こうなれば小細工は通用する魚ではないことははっきりと判ったので、膝を目一杯に落とし足腰を使いながら、ゆっくりとしたフットポンピングをする以外ない。5分が経過した。 |

|
実感のない夢 |

|
参考文献 写真帳 小笠原 倉田洋二 編 日本産魚類検索 全種の固定 中坊徹次 編 孤島の生物たち 小野幹雄著 |



