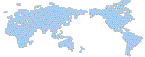
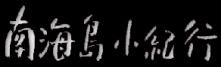 38回
38回
パラオ諸島釣紀

|
熱く美しい海である。 「パラオで青い海と虹は、名物で」とガイドの久米君がはにかむように言う。 |


|
若い人は南の島イコール釣りリゾートであるのだけれど、僕は南洋という言葉とともにサイパン、グァム、トラック、パラオ、ガダルカナル、ラバウル、レイテと玉砕の島を思い出してしまうのである。 戦後の生まれであるが、身近に感じるのは、僕だけであろうか。 |


|
久米君に小笠原で試した海の中でりリースする方法を教えると、すぐに実行し始めた。 |
|
|
僕は黙って、あと少しのラインを巻き取ってみた。スペーサーリーダー用に使っている22号、フロロカーボンラインは、スッパリとその限界点で切れている。 パラオの海はいつしか黄金色に変わり、マッシュルーム型の、小さな岩に近い島々の間をポートはかなり速い、スピードですり抜けて行く。僕はこの海、この島々、ここの魚が、大好きになった。 |
|
|
タックル ロッド: B.G. TUNA65、 B.G.
JACK、 GIANT88 リール: PENN9500ss、ダイワ EXi6000 ライン: モーリス・アヴァニー50Lb 取材協力 ベラウツアー |

